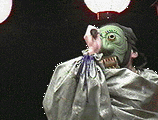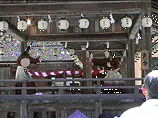森町の伝承する舞楽は、チベットやシルクロードの少数民族によって創始された芸能が、
仏教の伝来に伴って伝承され、中央の大寺社の法要に欠くことの出来ない行事となり
森町の神社にも伝播したものです。
天宮神社社伝によると、欽明天皇のときに創建し、文武天皇の慶雲2年(705)に舞楽が
伝わったという。
舞楽関係文書は、延宝五年(1677)鈴木武左衛門(小国神社禰宜)が記した指南書を貞
享二年(1685)に鈴木太良左衛門が書写、現在大場家に保存され、ほぼこれに従って舞
われている。
天宮神社十二段舞楽演目
一番:延舞(えんぶ) 七番:安摩(あま)
天の神、地の神、先祖の霊を 蔵面という紙でつくった面をかぶり
祀る清めの舞。延舞は振る舞の 笏を持ち、チャンチャノベットウ、
当て字で、神に供えるとか、 タッケラコーと唱歌を口ずさみながら舞う。
押し鎮める意味がある。
二番:色香(しきこう) 八番:二の舞
仏の舞といわれ、江戸時代には 咲面の翁と、腫面の媼が安摩の真似を
この舞人のみ神幸の列に加えられた しようとするがなかなかできない様子を
といい、大切な舞とされていた。 滑稽に演じる。「二の舞を踏む」という
諺は、この舞いが起源であるという。
三番:庭胡蝶(ていこちょう) 九番:陵王
4人の稚児が、蝶がゆっくり 竜頭をかぶり吊り顎のとがった
舞い遊ぶように舞う。 目の鋭い金色の面を付け、30cm余りの
桴を持って勇壮に舞う。
四番:鳥名(ちょうな) 十番:抜頭(ばとう)
4人の稚児が、姿・鳴き声ともに 稚児が天冠をつけ、金蘭綾織りの
美しい迦陵頻という幻の鳥が 装束で、桴を持って物静かに舞う。
舞い遊ぶさまを舞う。 黒紋付きの男が稚児を小脇に抱え楽屋に
連れ帰ると、白衣に変えた他の舞児が
男たちと争う「ザットラボウ」いい、
舞児を抱きかかえて楽屋に連れていく。
五番:太平楽 十一番:納曽利(なそり)
乱世を正すというめでたい舞い。 牙のある竜頭の面をつけ、右手に桴を持ち
俗に太刀舞。「太刀の一人舞い」は 竜の舞う様を表した活発な走り舞い。
独特の舞いです。

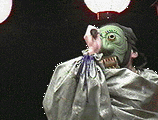
六番:新靺鞨(しんまか) 十二番:獅子
笏をもって舞い、この舞いを 貴徳面をつけた獅子伏せが大きな榊をかつぎ
「ヘラ」ともいう。 舞台を清める。獅子が登場し獅子伏せと
格闘となり獅子を退治する。
獅子伏せが鼻をかみ鼻紙を捨てる、見物人が
風邪除けのお守りとなるという鼻紙を
争って拾う。俗に「獅子伏せ」は悪魔調伏と
五穀豊穣を祈る舞いです。
小国神社十二段舞楽演目
番外:花の舞 七番:安摩の舞
一番:連舞 八番:二の舞
二番:色香舞 九番:抜頭舞
三番:蝶の舞 十番:陵王舞
四番:鳥の舞 十一番:納曽利舞
五番:太平楽 十二番:獅子舞
六番:新まっく舞

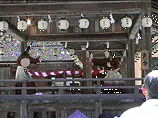
参考文献:遠江森町の舞楽「天宮神社十二段舞楽」(森町教育委員会)
遠江国一宮「小国神社」パンフレット(小国神社)
静岡県周智郡森町の芸能「舞楽装束」遠江国もりまち(森町教育委員会・森町史編さん室)